僕が中学高校の頃は「病院の診察室で風邪なんですと自分で病名勝手につけるとお医者さんにしかられるのは、医者のプライドにさわるからかな」となんとなく想像してました。今でもそう思っている人は多いとは思います。でも、医学部に入って医者になって現場にいると「自己診断つける患者と問答が長引いて時間とるのが大変に困る」というのが大きな理由だとわかってきました。患者の自己診断が結果として正解か不正解かは、たいしたことじゃないんです。
例を書いてみますと、症状を述べる患者A。
患者A :「この一週間、のどが痛くて、咳がでます」
医者:「なるほど、聴診しましょう」で、聴診開始まで10秒。
次の人 、自己診断タイプの患者B。
患者B :「この一週間、風邪ひいてるんです。風邪薬ください」
医者:「風邪だと思ったのは熱が出たからですか?」
患者B :「いや熱はないんです」
医者:「じゃあ鼻水とか?」
患者B :「鼻水はないんです」
医者:「咳とか痰はでますか?」
患者B :「咳はでます。とにかく風邪みたいな咳です」
医者:「のどは痛くないですか?」
(以下延々と問答。。。。。30秒経過、一分経過)
というこんな具合でして、ここでは風邪の話で書いてみたんですけど、なんというか、「この病名だから来ました」という人に症状の有る無しを結局最初から質問やりなおす時間を考えたら、医者も得しないし患者も得しないと感じる事が多いです。
しかも診察室での仕事って「よくある病気に、似ているけど、実は別の、重い病気」を否定することが重要なので「風邪のようだけど、喉頭がん、肺がん、治療困難な感染症」みたいなものと風邪とを区別する意味で、第一印象の「風邪っぽい」というヒントじゃ結局役に立たないわけですね。
参考資料としては、自己診断を医師に告げるのはありか(掲示板ミクル)でのやりとりや、医療情報の増加と患者さんの自己判断(医事紛争の事例)、そして本当は怖い思い込み・自己診断-乳癌も参考になります。
なお、精神科の場合だと、病名を患者に伝える事に慎重な意見も多くて「先生が病名を教えてくれないのですが」ページ内部の、「患者さんによっては病名を聞いただけで自殺を考える方もいます。」という精神科医林公一医師の文章は重みがあります。
おまけですけど、昔はよくいた「患者をどなるタイプの医者」今はめっきり減りましたね。実感で一割以下でしょうか。
今日の弁当は卵焼き、小松菜、大根とスモークサーモン。

自己診断は時間が損
 心と体
心と体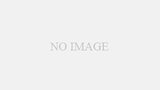
コメント
いきなり、でも平野先生あっなおひこさん
いまのモンスターペアレンツはすごいの。
主張を拒否するとはなれていくし、迎合すると
こっちが信じていることとちがうこと言ってる自分にパニクります。
ピアノのレッスンと診察いっしょにしては
これも怒られますね[E:virgo]
コメントありがとうございます。
「モンスターペアレンツ」問題も
時々僕の周りで耳にします。
ここ10年か15年くらいで増えたような
傾向はあるように思いますね。
ま、ピアノレッスンと診察じゃ別は別なんですが
「サービス業全般に対して、理不尽な要求をする利用者」
の悩みは増え続けてるという実感です。